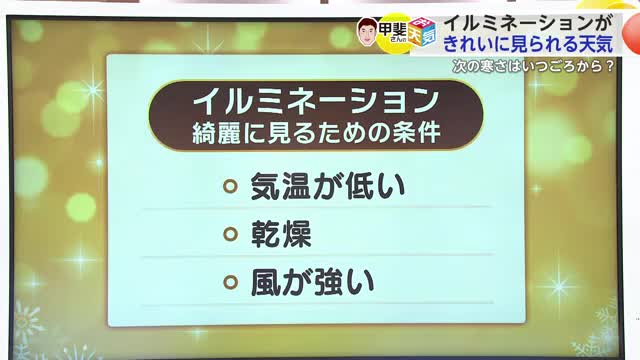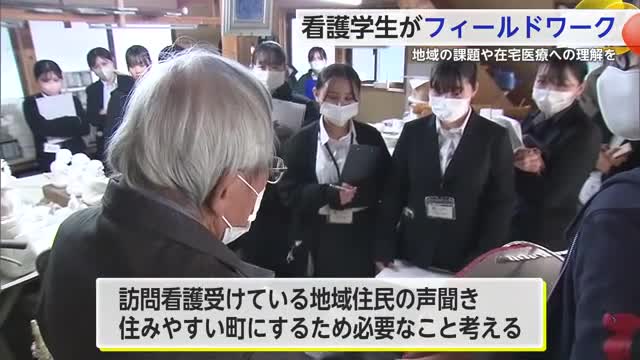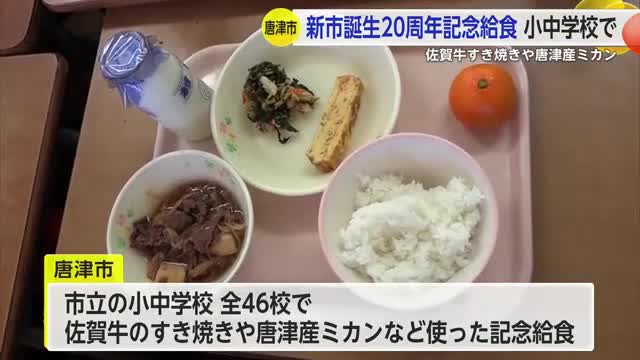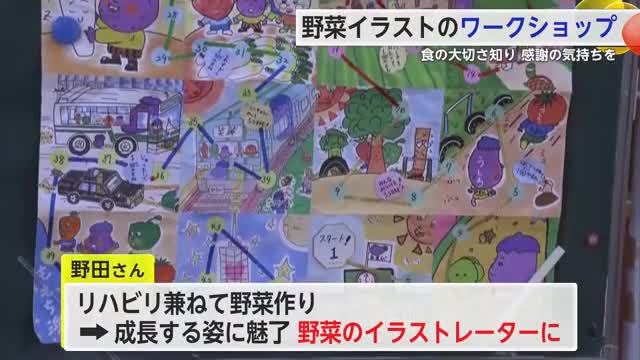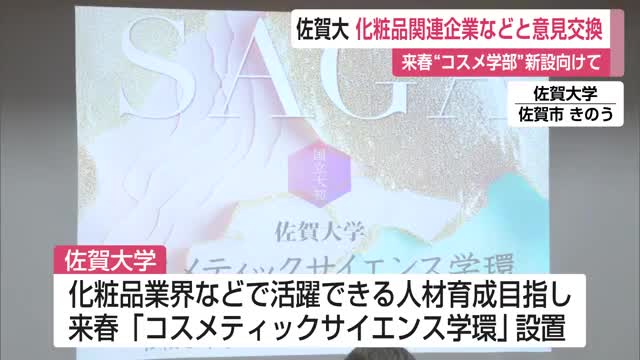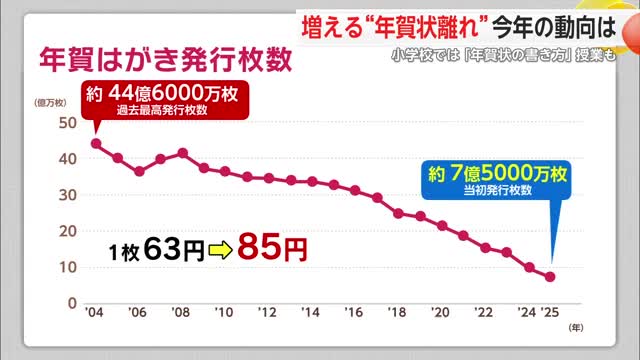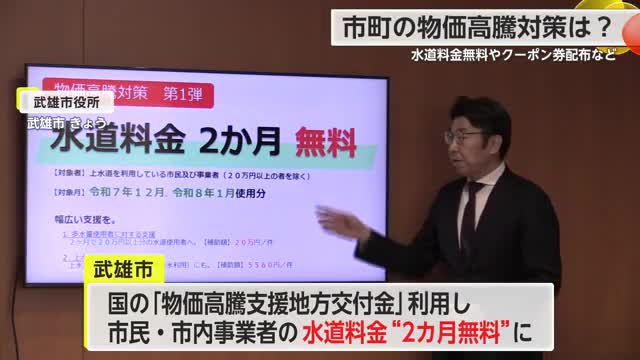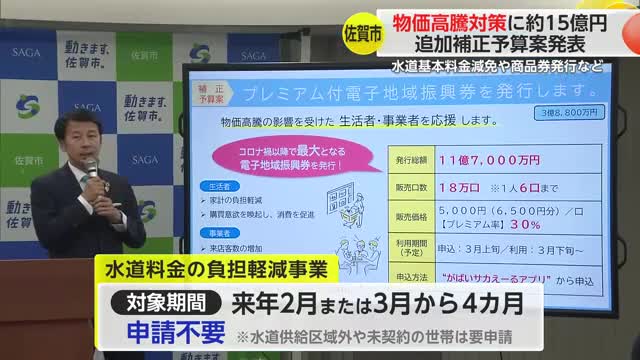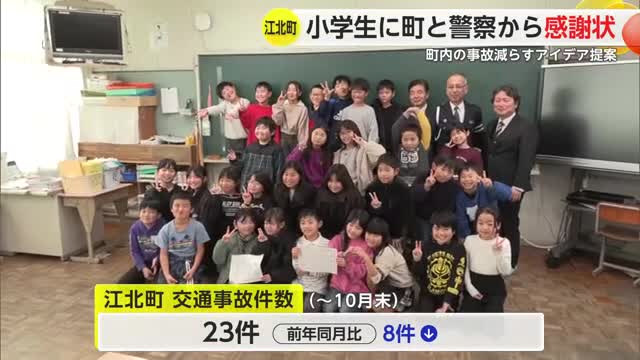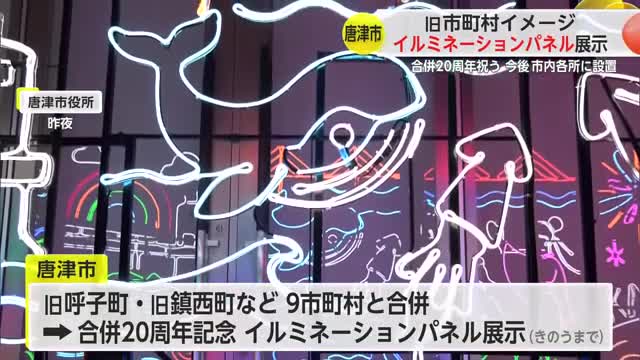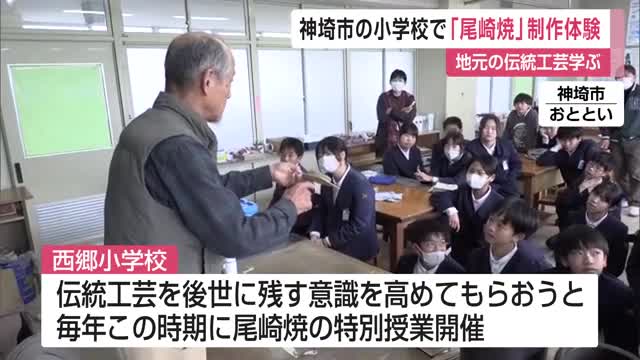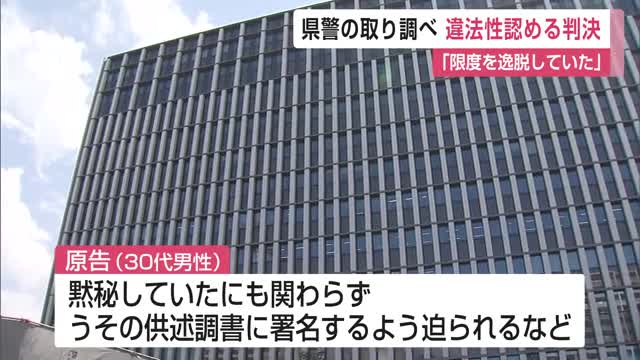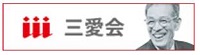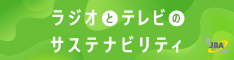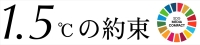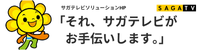佐賀のニュース
140年続く「夏休みの宿題」現代に合った在り方は?【佐賀県】
2022/08/29 (月) 18:30
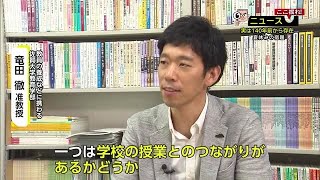
県内のほとんどの学校で2学期が始まりました。今回のニュースここ掘れは、みなさんが苦労した夏休みの宿題について考えてみます。
定番は「読書感想文、自由研究、絵日記」などですが、そのラインナップもここ数十年変わっていないようです。
解説主幹の宮原拓也さんです。宮原さん、素朴な疑問ですが、そもそも夏休みの宿題というのは、いつから始まったんですか?
【宮原拓也 解説主幹】
明治5年に学制発布されていまの学校制度がスタートし、その9年後に夏休みが始まりましたが、それと同時に宿題も始まっていますので、なんと140年の歴史があるんですね。
いま、子どもたちがやっている宿題をみてみましょう。以前とあまり変わっていませんね。
佐賀大学教育学部で、教員の養成や教師教育をしている竜田徹准教授に話を聞きました。
【宮原拓也 解説主幹】
夏休みの宿題について、全体の問題意識は?
【佐賀大学教育学部 竜田徹准教授】
一つは学校の授業とのつながりがあるかどうか。例えば1学期、7月までの授業で学んだことと宿題がつながっているか。8月後半から9月に始まっていく授業とうまくつながっていくか。もう一つは教師の反応。自分がせっかく頑張ったことに対して、教師からコメントとかあるといいが、はんこを押すだけで終わってしまうとか、そのままコンクールに出品して終わったとなると、子どもたちがせっかく頑張ったのに、という気持ちになってしまう。
【宮原拓也 解説主幹】
夏休みの宿題はドリル、読書感想文、自由研究というのが定番。これらの問題点は?
【竜田徹准教授】
自由研究のように比較的長期間かかるような課題とか、休みを利用して川とか山とか海とかに行ってできるような課題が出されることは大切なこと。
一方で問題点としては、子どもたちに十分な選択肢が与えられていなくて、一律に全員同じものをしなければいけない。子どものニーズとか、一人ひとりの好奇心や興味、関心の違いなどはあまり考慮されないまま、全員これをやってきなさいと、選択肢がないままに提供されているところがあって、その点が子どもの取り組みにくさにつながっているのではないか教科で限定するようなところもある。
例えば、理科や社会の枠でやってくださいと。私は国語(が専門)ですが、国語でも研究はできる。数学とか家庭科、調理の研究、体の動かし方、体育の研究もできる。理科とか社会に限ったものではない。
【鶴丸アナウンサー】
確かに、竜田先生が言われるように、モニターにある公立中のケースでも、自由研究は社会と理科ですね。
【宮原拓也 解説主幹】
どうしても自由研究となると、昆虫採集だとか天気調べ、あるいは地図づくりなど、社会や理科に偏りますが、ある意味、出題する側の先生たちもマンネリ化しているのかもしれませんでは、定番中の定番である読書感想文について聞きましょう。
【宮原拓也 解説主幹】
特に定番の読書感想文は先生が専門だが、読書嫌いになるのでは、とも言われる。
【竜田徹准教授】
読書感想文が国語嫌いとか読書嫌いを育てているのではないか、というのはずっと指摘されている7月までの授業で本を選ぶことや、文章の書き方の学習があると、すっと宿題に取り組める。同時に書いた文章が8月、9月の授業でクラスメートに読んでもらって、あーこんな本を読んだんだ、読んでみようかな、という学習があったり。先生からの反応、コメントが返ってくると、それだけでやってよかったなと思うが、そこまで行きついていないことが読書感想文をやらされてるだけ、こなすだけということになっている。
【宮原拓也 解説主幹】
アメリカでは「ブックリポート」といって、本を読んでみんなでプレゼン(説明)したり、ディベート(討論)したりということらしい。日本でもこういう動きはあるんですか。
【竜田徹准教授】
本を読んで語り合う授業をやったり、自分が読んだ本を数分間でプレゼンして、この本読んでみたいなと思った本に投票する「ビブリオバトル」という取り組みが、日本でも少しずつ授業とか学校行事のなかに入ってきている。本を読んだだけで終わるのではなく、読んだことを自分の言葉にして伝えて、相手からの反応を受け取るというフィードバックがある。だから取り組んでよかった、何のために本を読めばいいのかが分かるから、子どもも取り組みやすい。
【宮原拓也 解説主幹】
いま、全国では夏休みの宿題をなくす学校も出てきています。都市部では宿題の代行業者に任せて、夏休みはひたすら受験に費やすケースもあるそうです。これらは極論としても、小学校で英語が始まったり、夏休みが短くなっているのは事実で、おまけに塾の勉強もある佐賀市内の私立中学校の場合、夏休みは7月30日から8月16日までのわずか18日でした。特にコロナで外出もままならないという状況でもあり、貴重な夏休みも宿題漬けにするというのも考えものです。時代に合った宿題の在り方をどうするのか、去年と同じの前例踏襲ではなく、先生たち自身が大いに議論をして、知恵を出してほしいと思いますね。
定番は「読書感想文、自由研究、絵日記」などですが、そのラインナップもここ数十年変わっていないようです。
解説主幹の宮原拓也さんです。宮原さん、素朴な疑問ですが、そもそも夏休みの宿題というのは、いつから始まったんですか?
【宮原拓也 解説主幹】
明治5年に学制発布されていまの学校制度がスタートし、その9年後に夏休みが始まりましたが、それと同時に宿題も始まっていますので、なんと140年の歴史があるんですね。
いま、子どもたちがやっている宿題をみてみましょう。以前とあまり変わっていませんね。
佐賀大学教育学部で、教員の養成や教師教育をしている竜田徹准教授に話を聞きました。
【宮原拓也 解説主幹】
夏休みの宿題について、全体の問題意識は?
【佐賀大学教育学部 竜田徹准教授】
一つは学校の授業とのつながりがあるかどうか。例えば1学期、7月までの授業で学んだことと宿題がつながっているか。8月後半から9月に始まっていく授業とうまくつながっていくか。もう一つは教師の反応。自分がせっかく頑張ったことに対して、教師からコメントとかあるといいが、はんこを押すだけで終わってしまうとか、そのままコンクールに出品して終わったとなると、子どもたちがせっかく頑張ったのに、という気持ちになってしまう。
【宮原拓也 解説主幹】
夏休みの宿題はドリル、読書感想文、自由研究というのが定番。これらの問題点は?
【竜田徹准教授】
自由研究のように比較的長期間かかるような課題とか、休みを利用して川とか山とか海とかに行ってできるような課題が出されることは大切なこと。
一方で問題点としては、子どもたちに十分な選択肢が与えられていなくて、一律に全員同じものをしなければいけない。子どものニーズとか、一人ひとりの好奇心や興味、関心の違いなどはあまり考慮されないまま、全員これをやってきなさいと、選択肢がないままに提供されているところがあって、その点が子どもの取り組みにくさにつながっているのではないか教科で限定するようなところもある。
例えば、理科や社会の枠でやってくださいと。私は国語(が専門)ですが、国語でも研究はできる。数学とか家庭科、調理の研究、体の動かし方、体育の研究もできる。理科とか社会に限ったものではない。
【鶴丸アナウンサー】
確かに、竜田先生が言われるように、モニターにある公立中のケースでも、自由研究は社会と理科ですね。
【宮原拓也 解説主幹】
どうしても自由研究となると、昆虫採集だとか天気調べ、あるいは地図づくりなど、社会や理科に偏りますが、ある意味、出題する側の先生たちもマンネリ化しているのかもしれませんでは、定番中の定番である読書感想文について聞きましょう。
【宮原拓也 解説主幹】
特に定番の読書感想文は先生が専門だが、読書嫌いになるのでは、とも言われる。
【竜田徹准教授】
読書感想文が国語嫌いとか読書嫌いを育てているのではないか、というのはずっと指摘されている7月までの授業で本を選ぶことや、文章の書き方の学習があると、すっと宿題に取り組める。同時に書いた文章が8月、9月の授業でクラスメートに読んでもらって、あーこんな本を読んだんだ、読んでみようかな、という学習があったり。先生からの反応、コメントが返ってくると、それだけでやってよかったなと思うが、そこまで行きついていないことが読書感想文をやらされてるだけ、こなすだけということになっている。
【宮原拓也 解説主幹】
アメリカでは「ブックリポート」といって、本を読んでみんなでプレゼン(説明)したり、ディベート(討論)したりということらしい。日本でもこういう動きはあるんですか。
【竜田徹准教授】
本を読んで語り合う授業をやったり、自分が読んだ本を数分間でプレゼンして、この本読んでみたいなと思った本に投票する「ビブリオバトル」という取り組みが、日本でも少しずつ授業とか学校行事のなかに入ってきている。本を読んだだけで終わるのではなく、読んだことを自分の言葉にして伝えて、相手からの反応を受け取るというフィードバックがある。だから取り組んでよかった、何のために本を読めばいいのかが分かるから、子どもも取り組みやすい。
【宮原拓也 解説主幹】
いま、全国では夏休みの宿題をなくす学校も出てきています。都市部では宿題の代行業者に任せて、夏休みはひたすら受験に費やすケースもあるそうです。これらは極論としても、小学校で英語が始まったり、夏休みが短くなっているのは事実で、おまけに塾の勉強もある佐賀市内の私立中学校の場合、夏休みは7月30日から8月16日までのわずか18日でした。特にコロナで外出もままならないという状況でもあり、貴重な夏休みも宿題漬けにするというのも考えものです。時代に合った宿題の在り方をどうするのか、去年と同じの前例踏襲ではなく、先生たち自身が大いに議論をして、知恵を出してほしいと思いますね。
|
|
|
- キーワードから探す
佐賀のニュース
特集ニュース
DAILY NEWSランキング
こちらもおすすめ
全国のニュース FNNプライムオンライン
-
新潟県警の50代男性警部補がパワハラで懲戒処分「やってやるぞ、ボコボコにすっからな、死ね、自殺しろ」 2日間にわたって同僚を脅迫
2025/12/19 (金) 22:00 -
スキー場でロープウェーの救助訓練 緊急停止した場合を想定 救助用のカゴでゆっくり地上へ 岩手県雫石町
2025/12/19 (金) 21:55 -
週末は全国的に雨…北日本や日本海側も雪ではなく雨 西日本は10月下旬並み、北日本は11月上旬並みの気温予想も
2025/12/19 (金) 21:34 -
著名な日本人作家きっかけでうその株投資に勧誘 松山の女性が3100万円だまし取られる特殊詐欺【愛媛】
2025/12/19 (金) 21:30 -
JR八戸線が12月30日全線運転再開へ 沿線自治体などが早期復旧を要望 岩手県盛岡市
2025/12/19 (金) 21:25