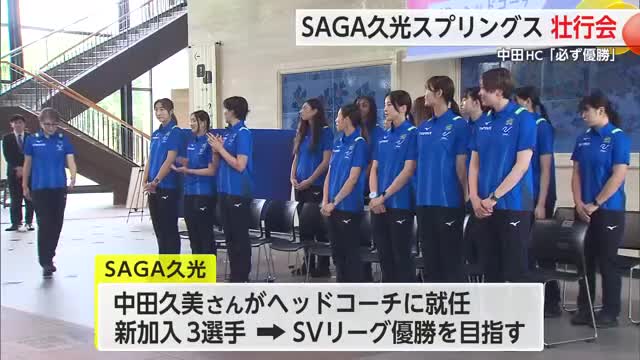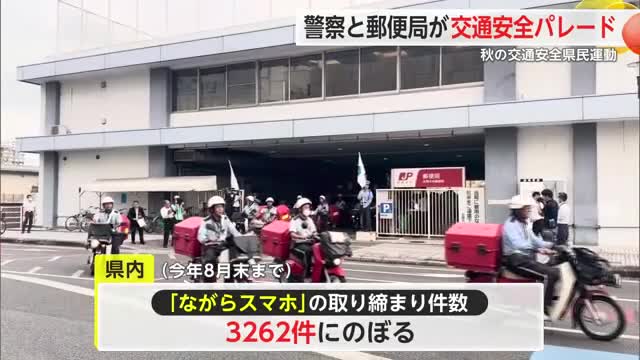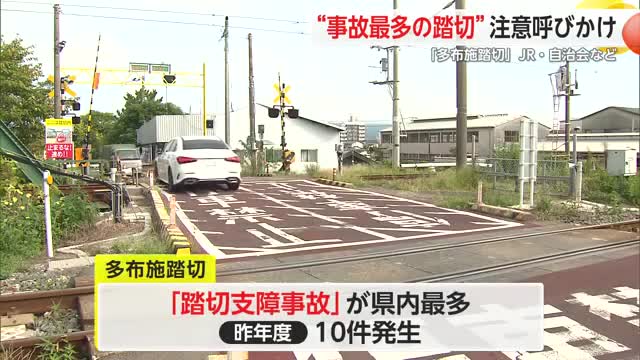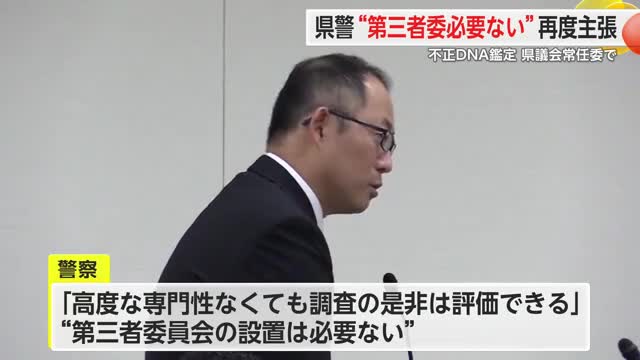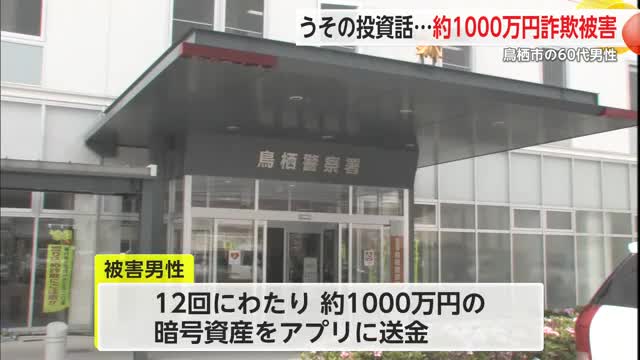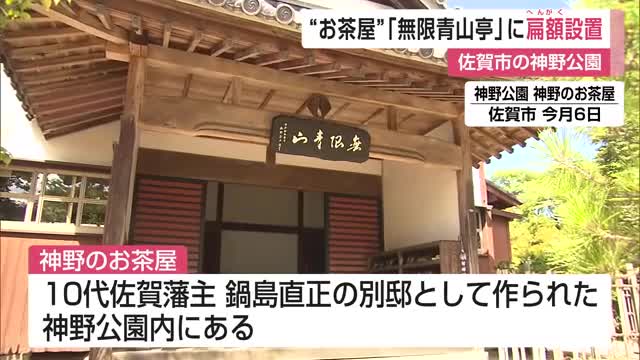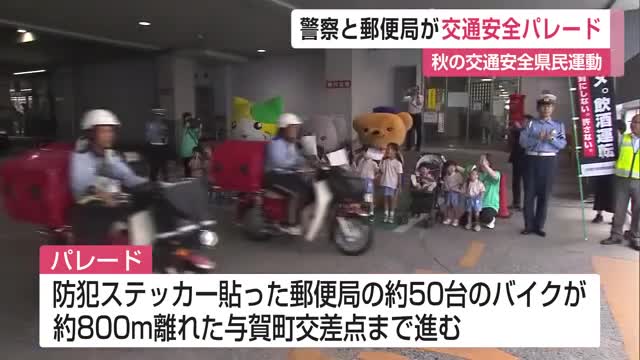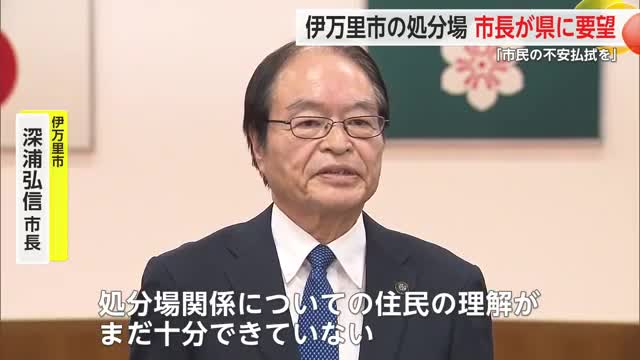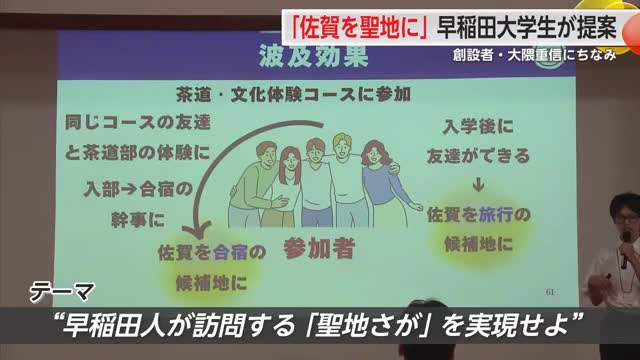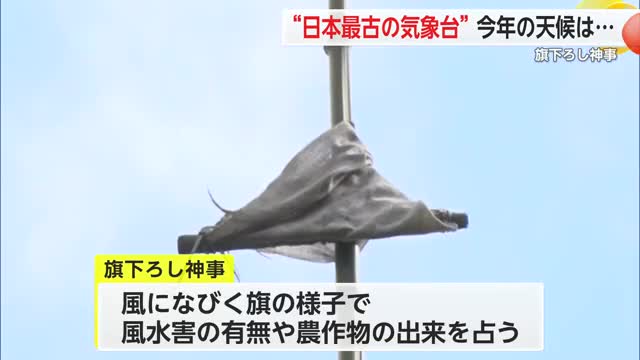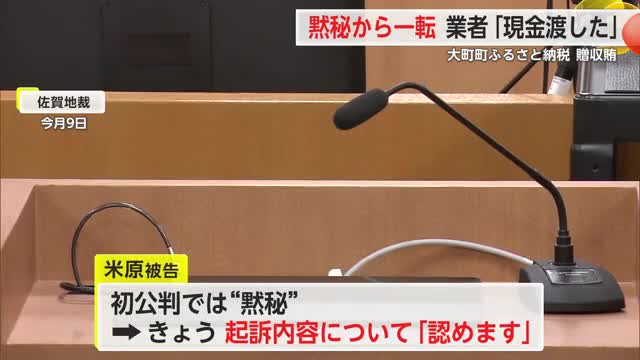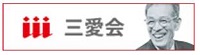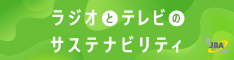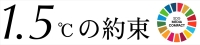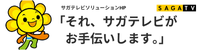佐賀のニュース
113人のまちに年に一度の祭り 伝統守る消防団員が奮闘 富士町下無津呂「放生会」【佐賀県】
2025/09/25 (木) 18:18

佐賀市の山あいにある人口約100人の集落で年に一度、地区の住民による祭りが開かれます。人口の減少や高齢化で地域行事が減る中、祭りを守り続けようと取り組む人たちの準備から当日まで密着しました。
佐賀市から車で1時間、木々に囲まれた富士町下無津呂。人口は約50年前の3分の1、113人が暮らしています。
【消防団 嘉村将孝さん】
「やっぱり静か、自然に恵まれているところ、交通の不便はありますけど、それを補う心地よさというか、自然のところが大好きです。」
年に1度、この町が活気にあふれます。毎年9月14日に行われる、「放生会」です。始まったのは50年以上も前。子供から大人まで神社に集まる、地域の交流の場です。
その運営の中心は地元の若者、日頃から下無津呂を守る消防団のメンバー7人です。平均年齢は36歳、何か月も前から準備に励んでいます。
本番1週間前のこの日、会場となる乳母神社に消防団員とOBが集まりました。
まずは重機で土を掘り起こし、木枠を設置、それから木の板を置いて・・・少しずつ完成形が見えてきました。出し物が披露される舞台は毎年手作りです。
Q.これどこから持って来たんですか?
【消防団 中原雄大さん】
【中原さん】
「山」
Q.何に使うんですか?
「舞台。柱とかにする。これ12メートル?13メートル」
汗だくで準備に励む消防団員。放生会の開催には特別な思いがありました。
2020年から3年間は新型コロナの影響で中止、翌年は大雨が下無津呂を襲いました。
Q.どんな影響があったんですか?
【消防団員 北川博之さん】
「山が崩れて民家の中に入ったりとか、そういうのもありましたので。」
Q.じゃあ祭りどころではなかった。
「そうですね」
Q.当時を振り返って
【消防団 嘉村将孝さん】
「うーん、言葉にならない。でも、どうにかしていかなきゃいけない。しゅんとするんじゃなくて・笑顔で楽しくやっていかないといけないよねっていうのがみんなの思いがあって、消防団が一丸となって『やりましょう』と」
災害を乗り越え、去年から放生会は再開。今年も9月14日を迎えました。
【消防団中原雄大さん】
「いやもうワクワクしかしとらんね。みんなが楽しんでもらえたらよかね」
Q.たくさん来てほしい?
「来てもらえたら嬉しかですね」
午後6時を過ぎ、続々と乳母神社に人が集まってきました。ブルーシートの上でお弁当を広げて食べたり話したりしながら楽しむのがここでのスタイル。下無津呂の人口とほぼ同じ、約100人が訪れます。
【訪れた人】
「もうちっちゃいときからずっとですよ。9月14日も決まり」
Q.放生会っていうのはどんな存在?
「やっぱり昔からの楽しみがひとつよね。だからみんなね、もう喜んで集まってくるしね」
【訪れた人】
「下無津呂の人がいっぱい考えて、出し物してくださって、そういうのは全部が楽しみで。」
佐賀市富士支所によりますと高齢化や人口減少で山あいの地区の集落の祭りは減少傾向といいます。
時代に合わせ、下無津呂の「放生会」も変化してきました。当初は下無津呂全体で1つの劇や映画を制作、35年ほど前からは地区ごとに出し物をするスタイルへ。
【嘉村真一宮総代】
「私が消防の部長をしていた頃に今までのやり方じゃちょっといけないなと思って。劇を一つずつ全部の地区どこでも出したらいいじゃないかということで始めたわけです。そういうことを考えてやったら成功してですね」
そしてコロナ禍を経て出し物は有志のみに。
【消防団 嘉村将孝さん】
「寂しい気持ちも、まあまあありますけど、じゃあどうやってみんなと楽しく今後やっていくかっていう、それが逆にバネになっている。」
Q.お祭りどう?
【小学生女の子グループ】
「たのしい!」「お肉が美味しかった」「可愛いだけじゃだめですか踊るのがめっちゃ面白かった。」「ジャンボリミッキーとかを踊れて楽しかったです。」「来年も来たい!!」
いつの時代も消防団が地域の祭りをつないできました。
【地元の人】
「人がだんだん減ってはいくんですけど、これを続けていこうという気持ちはやっぱり地区全体であるので、それに協力するという形ですよね。」
【地元の人】
「こういう祭りは残していったほうがいいと思いますね」
今年の放生会も無事に幕を閉じました。
【消防団 満行貢樹さん】
「みんな来てくれて本当に良かったなと思います。自分たちの思い出も昔からあるので、子供たちが大人になって同じように放生会したいなと思ってくれるようなこれからも運営ができたらと思っています」
【消防団 嘉村将孝さん】
「僕が知る限り今までない子どもの数でございました」
Q.過去一番の盛り上がり?
「じゃないかな、と。より楽しんで、ニコニコしてもらえるような、場を提供できたら」
Q.これからどれくらい続いていくといいなとかありますか?
「それはもう未来永劫ということで」
佐賀市から車で1時間、木々に囲まれた富士町下無津呂。人口は約50年前の3分の1、113人が暮らしています。
【消防団 嘉村将孝さん】
「やっぱり静か、自然に恵まれているところ、交通の不便はありますけど、それを補う心地よさというか、自然のところが大好きです。」
年に1度、この町が活気にあふれます。毎年9月14日に行われる、「放生会」です。始まったのは50年以上も前。子供から大人まで神社に集まる、地域の交流の場です。
その運営の中心は地元の若者、日頃から下無津呂を守る消防団のメンバー7人です。平均年齢は36歳、何か月も前から準備に励んでいます。
本番1週間前のこの日、会場となる乳母神社に消防団員とOBが集まりました。
まずは重機で土を掘り起こし、木枠を設置、それから木の板を置いて・・・少しずつ完成形が見えてきました。出し物が披露される舞台は毎年手作りです。
Q.これどこから持って来たんですか?
【消防団 中原雄大さん】
【中原さん】
「山」
Q.何に使うんですか?
「舞台。柱とかにする。これ12メートル?13メートル」
汗だくで準備に励む消防団員。放生会の開催には特別な思いがありました。
2020年から3年間は新型コロナの影響で中止、翌年は大雨が下無津呂を襲いました。
Q.どんな影響があったんですか?
【消防団員 北川博之さん】
「山が崩れて民家の中に入ったりとか、そういうのもありましたので。」
Q.じゃあ祭りどころではなかった。
「そうですね」
Q.当時を振り返って
【消防団 嘉村将孝さん】
「うーん、言葉にならない。でも、どうにかしていかなきゃいけない。しゅんとするんじゃなくて・笑顔で楽しくやっていかないといけないよねっていうのがみんなの思いがあって、消防団が一丸となって『やりましょう』と」
災害を乗り越え、去年から放生会は再開。今年も9月14日を迎えました。
【消防団中原雄大さん】
「いやもうワクワクしかしとらんね。みんなが楽しんでもらえたらよかね」
Q.たくさん来てほしい?
「来てもらえたら嬉しかですね」
午後6時を過ぎ、続々と乳母神社に人が集まってきました。ブルーシートの上でお弁当を広げて食べたり話したりしながら楽しむのがここでのスタイル。下無津呂の人口とほぼ同じ、約100人が訪れます。
【訪れた人】
「もうちっちゃいときからずっとですよ。9月14日も決まり」
Q.放生会っていうのはどんな存在?
「やっぱり昔からの楽しみがひとつよね。だからみんなね、もう喜んで集まってくるしね」
【訪れた人】
「下無津呂の人がいっぱい考えて、出し物してくださって、そういうのは全部が楽しみで。」
佐賀市富士支所によりますと高齢化や人口減少で山あいの地区の集落の祭りは減少傾向といいます。
時代に合わせ、下無津呂の「放生会」も変化してきました。当初は下無津呂全体で1つの劇や映画を制作、35年ほど前からは地区ごとに出し物をするスタイルへ。
【嘉村真一宮総代】
「私が消防の部長をしていた頃に今までのやり方じゃちょっといけないなと思って。劇を一つずつ全部の地区どこでも出したらいいじゃないかということで始めたわけです。そういうことを考えてやったら成功してですね」
そしてコロナ禍を経て出し物は有志のみに。
【消防団 嘉村将孝さん】
「寂しい気持ちも、まあまあありますけど、じゃあどうやってみんなと楽しく今後やっていくかっていう、それが逆にバネになっている。」
Q.お祭りどう?
【小学生女の子グループ】
「たのしい!」「お肉が美味しかった」「可愛いだけじゃだめですか踊るのがめっちゃ面白かった。」「ジャンボリミッキーとかを踊れて楽しかったです。」「来年も来たい!!」
いつの時代も消防団が地域の祭りをつないできました。
【地元の人】
「人がだんだん減ってはいくんですけど、これを続けていこうという気持ちはやっぱり地区全体であるので、それに協力するという形ですよね。」
【地元の人】
「こういう祭りは残していったほうがいいと思いますね」
今年の放生会も無事に幕を閉じました。
【消防団 満行貢樹さん】
「みんな来てくれて本当に良かったなと思います。自分たちの思い出も昔からあるので、子供たちが大人になって同じように放生会したいなと思ってくれるようなこれからも運営ができたらと思っています」
【消防団 嘉村将孝さん】
「僕が知る限り今までない子どもの数でございました」
Q.過去一番の盛り上がり?
「じゃないかな、と。より楽しんで、ニコニコしてもらえるような、場を提供できたら」
Q.これからどれくらい続いていくといいなとかありますか?
「それはもう未来永劫ということで」
|
|
|
- キーワードから探す
佐賀のニュース
特集ニュース